5月22日金曜日の夜は、「シロタ家の20世紀」という映画を、家人に誘われて観に行った。
20世紀の激動の歴史の縮図のようなウクライナ出身のユダヤ人家族、シロタ家を軸に描いた作品である。戦前期、日本で演奏と教鞭をとったピアニストのレオ・シロタ、日本で育ち米国に渡ったその娘のベアテ・シロタを軸としながら、その近縁の一族がデイアスボラのように、世界各地に散り散りにされながら、華やかで、残酷で苛酷な運命を描いた秀逸なドキュメンタリー映画である。
「ベアテの贈り物」を世に出した藤原智子監督の作品だ。帰宅後、制作パンフレットを読むと、この作品は、レオ・シロタ、ベアテ・シロタに関わり、教えられた実に多くの方々の協力と熱意が生み出した奇跡に近い産物であることが分かる。映画は制作費用が大変と聞く。この作品制作費用には、レオ・シロタの教え子の藤田晴子さんの遺された遺志が生かされているが、その経緯を知ると藤原さんが書いているようにまるで「天からの贈り物」だ。制作つくりの途上で、ある日東横線の列車で富田玲子さん(藤田晴子さんの遺産の管理を引き受けられた方)に藤原さんが偶然出会うことがなかったら、この作品制作はもっと厳しい道を歩んだだろう。そうしたエピソードが多く詰まっている。しかし、偶然を必然に変える力、藤原さんがこの映画をつくらないではおかない創造意欲に駆り立てる力を「シロタ家の20世紀」は持っていたということだろう。作品には、ベアテの従兄弟テイナの娘、アリーヌ・カラッソさんの証言、それに綾なすかのような実に多彩な人脈のつながりがひろがっていく。それに作品では表に出てこないが、パリやノルマンデイでの撮影や通訳、現地交渉に尽力された渡部忠男さんという方(カネボウのifシリーズを生み出した人物。現在は、パリ商工会議所・日仏経済交流委員会理事。パリ在住)の行動を知ると、胸が熱くなる。良い作品づくりに協力したいという心意気というか純粋な気持ちがひしひしと伝わってくる。たしかに、この作品は藤原智子さんというすぐれたドキュメンタリー映像監督の個性と、ベアテ・シロタ・ゴードンさんの人生に凝縮された人類の平和意思が生み出した第二の贈り物だ。ベアテというひとがいなかったら、無論この作品は生まれなかったし、何よりも、憲法24条はどうなったか分からなかったという、歴史における個人の役割、歴史の不思議を思う。だが、同時に日本国憲法(9条を核として)をつくらせた主人公は、あの悲惨な戦争を経ての人類の歴史的理性,「歴史の英知」であったというベアテ・シロタ・ゴードンさんの述懐は、肝に銘じて考えてみるべき重い示唆だ。
パンフの表紙裏のカントの次の言葉と、収録された訳者池内紀氏の「「世界市民」ということ」というエッセイも心に響く。
「永遠平和は空虚な理念ではなく、われわれに課せられた使命である」
(イマヌエル・カント 『永遠平和のために』 1795年、池内紀 新訳2007)
映画の主催は、北海道平和婦人会。I会長が挨拶されたが、いつものようにお元気だ。映画終了後、S駅近くのWホテル地下のおでん「かつや」に久しぶりに行く。地元食材が使われ、ほどよく味がしみて美味である。
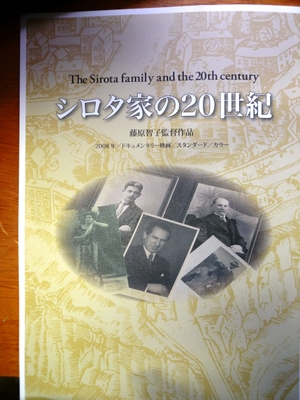

コメント