昨日、日曜日、朝からずっと机の前で作業をしていたせいか、午後も一定時間を過ぎてから、外に出て社会を呼吸したくなった。学会などが毎週のようにあって、家にいることが少なかった日曜日。このまま、我慢して、机に向かうか。プールに行って体を動かすか。しばらく映画館にも足を運んでいないので、映画を観るか。三択を自分に問うて見て、最後の選択がこの日の僕の好みとなった。新聞の映画館情報欄にさっと目を通し、時間を見て、街の中心を少し外れたところにある映画館には、家からは、地下鉄よりも、今から自転車で行けば間に合うと判断した。こうなると時間との勝負。急いで、着替える。車庫奥にある自転車は、タイヤが空気不足だ。これまた、手早く、タイヤにエアを入れる。さあ、めざす館へだ。重めの体を乗せて、我がクロスバイクを飛ばしてみた。16-7分走って、上映開始時間にギリギリセーフ。今日は、映画を二本はしごをするという欲張り計画。最初の方は、もう予告編が始まっている。地方都市の小劇場系映画館の良いところは、観客が割と少なく座れることだ。
最初の一本は、監督・原作・脚本・編集を一手に担った是枝裕和作品「歩いても 歩いても」だ。昨年6月に公開されて、見逃していた映画だ。
http://www.aruitemo.com/top.html

僕の下手な映画解説などしない方がよいが、ストーリーの展開は、冒頭の次の場面から始まる。
夏の終わり、湘南地方にあるらしい実家へ15年前に亡くなった兄の命日へ、次男が妻と息子を伴って訪ねて行く。・・・
そこから展開される、淡々とした中に、長男を喪った老親と、次男、長女の家族の確執や愛情と憎しみ、それに思いやり。重さも軽さもある会話と家族の情景。是枝監督の「誰も知らない」に見られたリアルで細やかな視線は、この作品にも貫かれている。多分懐かしさをこの作品に感じるのは、小津安二郎、成瀬巳善男監督たちの作品が持っていた日本映画の家族劇の良質のテーストをこの作品も含んでいるからなのだろう。
感想を少しだけ書いておこう。映画のちらしには、「家族のことを想う時、何度でも観たくなる映画です」とある。鑑賞後、入手した映画パンフレットの川上弘美の解説にも、「いい映画はたくさんある。でも、この映画のように、その中にいる人たちのことを、今もずっと考えつづけている映画を、わたしは見たことがない」とある。素直に、そうだなと思う。阿部寛、夏川結衣、YOU、高橋和也、田中祥平、樹木希林、原田芳雄が主な出演者だ。
僕のもう若くはない年齢が、もはやそのような視線にさせるのか、どちらかといえば主人公の阿部、夏川が演じる次男夫妻の視点よりも、樹木希林、原田芳雄が演じる老親の方に情感が寄せられる。樹木と原田のセリフ回しのさりげない毒にゾクッとするのだ。そして、次男夫妻の妻の連れ子の高橋祥平のまなざしは、そうした大人たちを相対化して見つめていて、どこか監督がもつ目線のようでもある。家族は互いに、愛憎の中で、ぶつかり合いながらも、子や孫のどこかで受け継がれていく。
余韻を含んで、銀幕が降りて、館外に出る。同じフロアの今度は別のシアターで二本目だ。20分ほど待って、今度は別のテーストの作品。しかし、映画の焦点は、現代の家族と子どもの貧困、それと社会のセーフテイネットの問題だ。映画のタイトルは、「ベルサイユの子」(ピエ-ル・ショレール監督)。
http://www.zaziefilms.com/versailles/#alive
 重たいテーマだ。映画案内に書かれたストーリーを転記するとこうだ。
重たいテーマだ。映画案内に書かれたストーリーを転記するとこうだ。
<・・パリの街をさまよった末、ベルサイユ宮殿近くの森にたどり着いたホームレスの母子。二人は社会からはみ出て生きるダミアン(ギョーム・ドパルデュー)と出会うが、母親は5歳のエンゾ(マックス・ベセット・ドゥ・マルグレーヴ)を置いて姿を消す。予期せぬ事態に困惑するダミアンだったが、生活を共にするうちに親子のような情愛が芽生えていく。・・>
フランスの社会的排除の現実が否応なく画面に出てくる。社会から森の中に追い出されて住む人々は、ダミアン(ギョーム・ドパルデュー)のように、家族の絆から切り離されていたり、貧困が故であったり、恐らくはロマ(ジプシー)の人々であったりだ。それを忌み嫌う人々の存在もある。他方、フランスの法は、社会的排除を禁止し、子を持つ親の生活保護を受ける権利や最低限の社会保障システムを持ち、エンゾ(マックス・ベセット・ドゥ・マルグレーヴ)の母ニーナ(ジュデイット・シュムラ)のようなうち捨てられ、クズ扱いされた人の社会的自立を援助するNGO組織も存在する。しかし、そこからこぼれてしまう人たちも多くいる。最後は、人のもつ人間的愛の感情だ。エンゾ(マックス・ベセット・ドゥ・マルグレーヴ)は、親の養育力の限界と社会保障システムの機能不全のその隙間に落ちたが、ベルサイユの森に入り込んだ母が、そこに暮らすダミアン(ギョーム・ドパルデュー)に本能的にこの人ならと託した結果、かろうじて生き残る道につながっていった。しかし、エンゾが大きくなっていき学齢期になることで、ダミアンは森の生活をやめて、折り合いの悪い父の家に行き、家賃を払いながら、エンゾを学校に行かせ育てる道を選ぶ。法的に、養育親権を得て、一応エンゾの見通しがついた時点で、ダミアンは、再び、父の家を出る。エンゾは、ここで、ダミアンにも置いて行かれ、ダミアンと折り合いの悪かった父ジャン・ジャック(パトリイク・デカン)とその若い妻の元で育てられる。映画のまなざしは、エンゾは、このまま、成人していけば、恐らくは、人間不信と信頼の間をずっと悩み続ける人生を送ることになったであろうと思わせる。(そういうケースが多いのかも知れない)しかし、この映画の最後の救いは、ダミアンが去ってから7年後に、立ち直った母が引き取りに現れたことだ。・・その先はどうなっていくのだろう?というところで、映画は終わる。
是枝監督の「誰も知らない」の世界と、この「ベルサイユの子」の世界は、海を隔て、地理的にも文化的にも遠い。しかし、グローバル化した現代においては、事柄の本質は、同じである。厳しい条件に置かれた子の生きる権利は、うち捨てられてはならない。なんとしても、社会で守り、そして何よりも親が守れるように、その環境を整える必要があるのだと。
主演したギヨーム・ドパルデュー(Guillaume Depardieu)は、名優ジェラール・パルデユーの息子であり、(どこか似ていると思った)昨年この映画公開後、ルーマニアでの別の映画撮影中の急性肺炎で、パリに移送されるも、37歳で夭折したのだという。痛ましくも惜しい。
内容の濃い作品を2つも観て、やや心も濃密な印象に満たされた。帰りの自転車で、ネオンや居酒屋の喧噪に包まれた街を抜けて行くと、ここ」には北の大地の別の現実があるのだと思った。しかしどこかで2つの映画とつながっていく現実でもあるのだ。そういうことの簡明な事実に気づかされるのはいつも少ししてからだ。「歩いても 歩いても」(いしだあゆみの「ブルーライト横浜」のさびの一フレーズだ)の映画ではないが、「人生は、いつでもちょっとだけ間に合わない」ようにできているのかも知れない。ある事柄をそれとしてしかと気づいていくには、多少のタイムラグがあるのだ。僕のような凡人は、いつもその気づきの遅さ(悔しいね!)を抱えて生きていくしかないのだろう。
![]() 名の加盟があった。久しぶりの嬉しいニュースだ。とくに、非正規の方の新規加盟は、現在の仕事の実情などをお聞きする機会を設け、分班の執行委員が丁寧に懇談や聞き取りを続けられた中での成果だ。前に書いたように、大学の経営効率化の名の下に、非人間的な人件費圧縮が、まかりとおってきた。これを実際に是正する効果ある運動が求められている。あたりまえのことが通る職場をつくることが肝心だ。僕も及ばずながら全学の組合執行委員選挙が終わり、信任され次期執行部三役に仲間入りすることになった。一次会の散会のあと、あたらしく加盟された方々とともに、二次会に出かけた。この日は、楽しい語らいと酔いだった。
名の加盟があった。久しぶりの嬉しいニュースだ。とくに、非正規の方の新規加盟は、現在の仕事の実情などをお聞きする機会を設け、分班の執行委員が丁寧に懇談や聞き取りを続けられた中での成果だ。前に書いたように、大学の経営効率化の名の下に、非人間的な人件費圧縮が、まかりとおってきた。これを実際に是正する効果ある運動が求められている。あたりまえのことが通る職場をつくることが肝心だ。僕も及ばずながら全学の組合執行委員選挙が終わり、信任され次期執行部三役に仲間入りすることになった。一次会の散会のあと、あたらしく加盟された方々とともに、二次会に出かけた。この日は、楽しい語らいと酔いだった。 雨粒を含んだ花弁の間をトンボが動き、モンシロチョウが舞っている。
雨粒を含んだ花弁の間をトンボが動き、モンシロチョウが舞っている。










































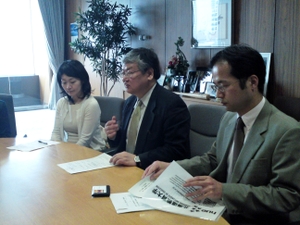
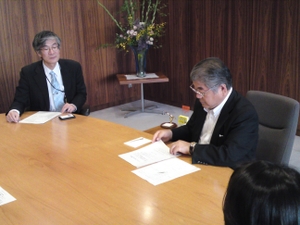







最近のコメント